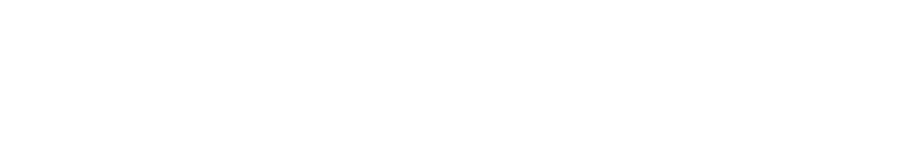相手に配慮できる子は国語ができる
まなび研究所のLINEに上がってくる問題演習シート(中学生)を見ていると、写真が暗かったり、全体が写っていなかったり、字が薄くて読みにくかったり…そんな光景に出くわすことがあります。
この現象、実は国語力と密接に関わっているんです。
国語ができる子どもたちの特徴として、「相手の立場に立って考える力」が自然と身についていることが多いと感じています。これは偶然ではありません。国語の学習において、登場人物の心情を読み取ったり、筆者の主張を理解したりする過程で、自分とは異なる視点や立場に立つ経験を重ねているからです。
問題演習シートの写真一つとっても、相手がどう見るかを想像できる子は、自然と「見やすく撮るにはどうしたらいいか」を考えられます。明るい場所で、全体が写るよう調整し、文字がはっきり見えるように撮る。これは単なる写真技術ではなく、「相手に伝える」という意識の表れなのです。
逆に言えば、こうした配慮が欠けている場合、それは国語力の一側面に課題があるサインかもしれません。テキストの読解だけでなく、相手の立場に立って想像する力、つまり「読者意識」が育っていないことを示しています。
子どもの国語力を高めるには、単に漢字や文法を教えるだけでなく、日常生活のあらゆる場面で「相手にどう伝わるか」を意識させることが大切です。例えば、問題演習シートを撮影する際に「先生に見せるつもりで撮ってみよう」と声をかけるだけでも、意識は変わってきます。
また、自分の書いた文章を家族に読んでもらい、「わかりにくかったところはどこか」を聞いてみるのも効果的です。フィードバックを受けることで、自分の表現が相手にどう伝わるかを実感できるでしょう。
「言葉の豊かさは思考の豊かさに直結する」という言葉を大切にしています。
先日、ある生徒が期末テストの勉強のために撮った週間スケジュール表の写真が、いつもと違って驚くほど見やすかったことがありました。「どうしたの?」と尋ねると、「前回先生が見づらいって言ってたから、今日は窓際で撮りました」と。その生徒は、国語の成績も着実に上がっていました。相手を思いやる気持ちと国語力は、確かに連動しているのだと実感した瞬間でした。
国語力を高めることは、学力向上だけでなく、他者との関係構築にも大きく影響します。そして、その基盤となるのは「相手の立場に立って考える力」なのです。お子さんの国語力を磨きながら、同時に思いやりの心も育んでいけたら、それこそが真の教育ではないでしょうか。
日々の小さな気づきから、子どもたちの大きな成長が始まるのです。
2025/03/28 Category | blog