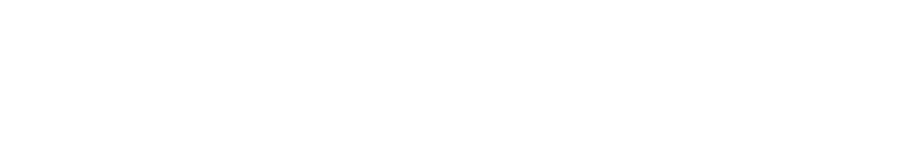中学生になる子どもを自立へ導く家庭での接し方
春になると教え子たちが、まなび研究所に訪ねてきてくれます。進学や新生活の報告を聞きながら、彼らの成長に心が温かくなります。「行動経済学を学び、犯罪を抑制するまちづくりをしたい」「医大に進み、地域医療に従事したい」「国連で働き、世界から差別をなくしたい」—こうした明確な志を語る姿に、教育の本質を見る思いがします。
中学生になるとき。これは子どもの人生における重要な節目です。単に小学校から中学校へ進学するだけではなく、思考や行動が大きく変わる時期です。この時期をどう過ごすかが、お子さんの将来を左右するといっても過言ではありません。
「自立」とは何か
自立とは単に「自分のことは自分でする」という意味ではありません。自分で考え、判断し、責任を持って行動できること。そして何より、自分の人生に対して主体的に関わることです。
教え子たちが立派な志を持てたのは、「何のために勉強するのか」という問いを繰り返し考え、たくさんの本を読み、自分なりの答えを見つけたからです。
まなび研究所は、開塾当初から「Read more, learn more, change the globe」というメッセージを発信し続けています。このメッセージには、「もっと本を読もう、もっと学ぼう、そして世界を変えよう」という思いと自立することの素晴らしさも込めています。
家庭での具体的な接し方
1. 対話の時間を増やす
中学生になると、友人関係や学校での出来事を親に話さなくなる傾向があります。だからこそ、意識的に対話の機会を作りましょう。夕食の時間や休日の朝など、家族が集まる時間に「今日はどんなことがあった?」「最近考えていることは?」と問いかけてみてください。
先日、ある保護者から「子どもが反抗期で会話が減りました」という相談を受けました。そこで提案したのは「子どもの心になって考えてみること」でした。その保護者は、子どもの趣味だったゲームについて調べ、「このキャラクターのデザインがすごいね」と会話を始めたところ、子どもが目を輝かせて語り始めたそうです。共通の話題を見つける努力が、対話の扉を開くのです。
2. 読書の習慣を共に育む
自立した思考を育むために、読書ほど効果的なものはありません。しかし「読みなさい」と言うだけでは逆効果です。
まずは親自身が読書する姿を見せましょう。そして本の内容について「この主人公の決断をどう思う?」「もし自分だったらどうする?」と意見を求めてみましょう。正解を求めるのではなく、考えるプロセスを大切にします。
3. 失敗を恐れない環境を作る
自立とは「完璧であること」ではありません。失敗し、そこから学ぶ過程こそが大切です。テストの点数が悪かったときも「どうしてできなかったの?」と責めるのではなく、「次はどうすれば良くなると思う?」と問いかけることで、自分で考える力を育みます。
4. 家事や家族の一員としての役割を与える
洗濯物たたみ、食器洗い、ゴミ出しなど、家族の一員としての役割を持たせましょう。これは単なる手伝いではなく、社会の中で責任を果たす練習です。役割を通じて「自分は必要とされている」という実感が、自己有用感を育みます。
5. 「なぜ勉強するのか」を一緒に考える
多くの中学生が「なぜ勉強するのか」という疑問を持ちます。この問いに対して「いい高校に入るため」「将来のため」という抽象的な答えではなく、具体的な視点で考えてみましょう。できれば、10年後、20年後に、どのようにして社会課題を解決をしているのか。言うなれば、将来、社会をより良くするために勉強するという視座です。
世界には様々な社会課題があります。環境問題、貧困、差別など。「あなたはどんな問題に関心がある?」「それを解決するためにはどんな知識や技術が必要だと思う?」と問いかけてみてください。勉強が単なる点数獲得の手段ではなく、世界をよりよくするための道具だと気づくきっかけになります。
6. 選択肢を与え、決断する経験を積ませる
小さなことからでも構いません。「今日の夕食は何にする?」「週末はどこに行きたい?」など、選択し決断する機会を増やしましょう。その際、メリットとデメリットを一緒に考えることで、判断力も育ちます。
親が変わることの大切さ
子どもの自立を促すには、親自身の変化も必要です。ある母親は「子どもが自分で考えない」と悩んでいました。よく話を聞くと、その母親自身が子どもの小さな判断まで先回りして指示を出していました。そこで行動を改め、何があっても子どもを信じて見守る姿勢に変えたところ、子どもが少しずつ主体的に動き始めたのです。
おわりに
子どもの自立は一朝一夕に実現するものではありません。時には後退することもあります。でも焦らず、子どもの可能性を信じて見守ることが大切です。
子どもが自立するとき、親子関係は「教える-教わる」から「共に学び、共に成長する」関係へと変わります。それは子どもだけでなく、親自身の人生も豊かにしてくれるでしょう。
中学生という多感な時期。親として何をすべきか、何をすべきでないか、ぜひご家庭で考えてみてください。そして何より、子どもの心に寄り添い、共に成長する喜びを感じてください。
2025/03/29 Category | blog