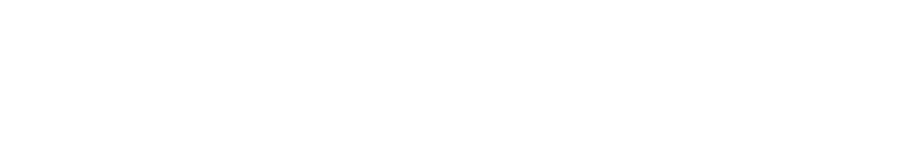自分で丸つけができる受験生は成長が早い
お子さんは問題を解いた後、自分で丸つけをしていますか?
中学受験や高校受験を目指すお子さんを見ていると、ある特徴に気づきます。成績が伸びる子と伸び悩む子の違いは、実は「自分で丸つけができるかどうか」にあることが多いのです。
なぜ自分で丸つけができないとミスが減らないのか
問題を解いて、答え合わせをするまでに時間が空いてしまうと、どうなるでしょう?
「あれ、この問題はどう考えたんだっけ?」 「この計算、なんでこうなったんだろう?」
解いた直後なら鮮明に覚えている思考プロセスも、時間が経つと曖昧になってしまいます。特に小学生や中学生は、問題を解いたときの思考を長時間保持することが難しいものです。
ミスの原因を正確に把握できず、同じミスを繰り返す—これが丸つけを後回しにする子に見られる典型的なパターンです。
学習サイクルを早く回す効果
問題を解いた直後に丸つけをすると、どのような効果があるでしょうか?
- 即時フィードバック: 「あ、ここで間違えたんだ」と気づくのが早い
- 思考の鮮度: 解いたときの考え方が鮮明なうちに修正できる
- 記憶の定着: 間違いとその修正が一連の流れで脳に刻まれる
- モチベーション維持: 小さな成功体験が積み重なる
この「学習→テスト→フィードバック→修正」というサイクルを早く回せば回すほど、お子さんの成長スピードは加速します。
浜松西高中等部に合格した生徒の例
浜松西高中等部に通うAさんは、数学の問題集を解く際、1ページ解いたらすぐに答え合わせをし、間違えた問題はその場で解き直していました。
「解く→すぐ丸つけ→修正→次に進む」というリズムが身についていたAさんは、同じミスを繰り返すことが少なく、効率よく実力を伸ばしていきました。
お子さんの丸つけ習慣を育むには
「うちの子は丸つけをすぐにしない…」とお悩みの親御さんも多いでしょう。では、どうすれば良いでしょうか?
先日、ある保護者の方から相談を受けました。「子どもが丸つけを嫌がって、問題ばかり解いています」と。
お子さんが丸つけを避ける心理を考えてみましょう。多くの場合、「間違いを見たくない」「赤ペンでバツをつけるのが嫌」といった気持ちがあります。
ならば、丸つけのイメージを変えてみませんか?
- 丸つけは「間違い探し」ではなく「成長のチャンス発見」と考える
- 最初は親子で一緒に丸つけを行い、その場で「なぜ間違えたのか」を話し合う
- 丸つけした後に「次はこうしよう」と具体的な改善策を考える習慣をつける
- 正解数ではなく、ミスから学んだことを評価する
小さな成功体験を積み重ねることで、お子さんは自然と「すぐに丸つけをする」習慣を身につけていきます。
振り返りの質が学びの質を決める
勉強の真の価値は、問題が解けたかどうかではなく、ミスから何を学んだかにあります。「振り返りの精度が高い子は伸びる」と私はいつも感じています。
お子さんに問いかけてみてください。
「今日の勉強で、どんな新しい発見があった?」 「間違えた問題から、何を学んだ?」
丸つけを通じて、お子さんが自分の思考プロセスを振り返る習慣がつけば、学習の質は格段に向上します。
そして何より大切なのは、丸つけの過程でお子さんが自分自身の学びに責任を持つこと。これは単なる学習習慣の問題ではなく、「自分の成長は自分でコントロールできる」という主体性を育む過程なのです。
皆さんのお子さんは、問題を解いた後、どのタイミングで丸つけをしていますか?もし後回しにする傾向があるなら、今日からちょっとした工夫で変えていけるかもしれません。
お子さんと一緒に、学習サイクルを早く回す方法を考えてみませんか?
2025/03/31 Category | blog