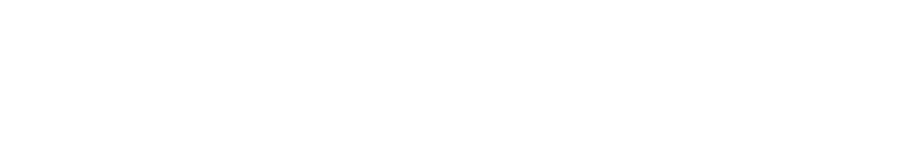極上の文章に触れる体験 〜春の読書講座「ゴッホの手紙」から〜
まなび研究所の玄関には、レゴブロックで作った「星月夜」の作品が飾られています。渦を巻く青い夜空と輝く星々、小さな村の姿まで、色とりどりのブロックで表現されていて、訪れる人の目を引きます。
春の読書講座 では、小学5、6年生たちと「ゴッホの手紙」を読み解く時間をもちました。西洋絵画の巨匠として知られるゴッホが、生涯にわたって弟テオに宛てた数々の手紙には、彼の内面、芸術への情熱、兄弟の絆が色濃く映し出されています。
子どもたちの目が輝いた瞬間
教室に集まった子どもたちの表情は、最初は少し緊張気味でした。「ゴッホってどんな人?」「なぜ手紙を読むの?」という疑問が浮かんでいるようでした。
しかし、ゴッホが弟テオに向けて書いた言葉を紹介していくと、次第に子どもたちの目が真剣になり始めました。
「日本の浮世絵には真実がある」 「僕は日本の芸術から多くを学んでいる」 「日本の芸術家たちの線の明快さと色彩感覚に驚嘆する」
こうした言葉の一つ一つに、子どもたちは耳を傾け、ときには「なんで浮世絵なの?」「お金がなかったのに絵を描き続けたの?」と鋭い質問を投げかけてくれました。
感性を広げる読書体験
子どもたちはゴッホが描いた「星月夜」を想像してもらいながら、彼の日本美術への憧れと自作への影響を考えました。「星月夜」の渦巻く青い空と輝く星々を見た時、一人の子が「これって北斎の波みたいだね」とつぶやき、教室に静かな発見の喜びが広がりました。日本の浮世絵がゴッホの絵画表現にどう影響したのかを、子どもたちなりに感じ取っていたのです。
文章を読み、それを視覚的なイメージと結びつける体験は、子どもたちの感性を大きく広げます。それは教科書の文章を「理解する」こととはまったく異なる体験です。
私が「ゴッホは弟のことをすごく大切にしていたんだね」と言った時、教室に深い共感が広がりました。芸術家の苦悩や愛情を感じ取る心が、確かに育まれていると感じた瞬間でした。
極上の文章が子どもを育てる理由
極上の文章や芸術作品に触れることは、子どもたちの感性を研ぎ澄まし、想像力を育みます。それは単なる知識の習得ではなく、心の成長につながるものです。
考えてみれば当然のことかもしれません。子どもたちの脳や心は、与えられた「栄養」によって形作られていくのですから。
文字からイメージへ、そして共感へ
読書講座の終わりに、私は子どもたちに「ゴッホの作品を模写してみよう」という提案をしました。最初は「えっ!」と、子どもたちの間に戸惑いが広がりましたが、すぐに「それも面白そう」という空気に変わっていきました。北斎や広重の浮世絵に影響を受けたゴッホの構図や色彩を、子どもたちなりに捉えようとする姿を想像するだけでワクワクしてきます。ある子は「星月夜」の渦巻く星空を、別の子は「花咲く梅の木」の繊細な枝ぶりを真似て描くのだろうな。模写という行為を通して、ゴッホの日本美術への憧れを体感的に理解してほしいという願いを込めました。
この春の読書講座を通して、改めて感じたことがあります。子どもたちは「難しそう」と思われる文章でも、その中に真実や美があれば、驚くほど深く理解し、感じ取る力を持っているということです。このことをゴッホが教えてくれたように感じます。
教科書の文章だけでなく、時代を超えて人々の心を動かし続ける「極上の文章」に触れる機会を、もっと子どもたちに提供していきたいと思います。そうした体験が、やがて彼らの人生を豊かにする大きな力となるはずですから。
子どもたちが帰りがけに「また読書講座を受けたい」と言ってくれたことが、何よりの喜びでした。
皆さんのお子さんも、ぜひ「難しそう」と思える本に挑戦してみてください。その先に広がる世界は、想像以上に豊かなものかもしれません。
2025/04/01 Category | blog