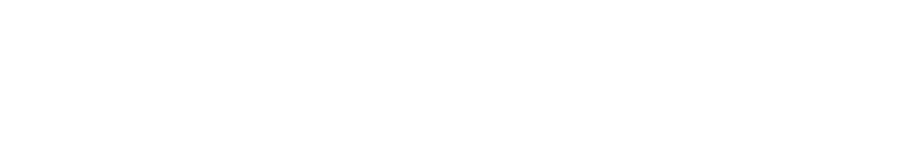【4/1付】意見を育てるニュース教室 – 言葉の力を磨く
子どもたちが自分の意見を持ち、それを適切に表現できる力を育むこと。この力は、将来どんな道に進んでも欠かせない財産になります。私は「将来何をしたいか」ではなく「将来どうありたいか」を子どもたちに考えさせたいのです。
意見を育てるニュース教室 では、児童たちが関心を持ったニュースについて考え、自分の言葉で80字の作文にまとめています。小川先生によると、今週児童たちが興味を示したのは「食品・日用品の値上げ」「サッカー日本代表のW杯出場権獲得」「京都市の琵琶湖水への感謝金」「女性警官の制服スカート廃止」など、多岐にわたるテーマでした。
授業では、提出された作文から特に注目すべき点として、「小数1.5と単位kmの原稿用紙での書き方」と「『すごい車』という表現が示す具体的なイメージ」を取り上げました。
小数の書き方については、ある児童がすぐに挙手し、「数字を漢数字に直し、数字も小数点も1マスずつに書く」という完璧な回答を出しました。単位については複数の意見が出ましたが、特筆すべきは5年生が正解を答えたことで、これは6年生たちに良い刺激となりました。
「すごい車」については「大きい車」「高価な車」「きれいな車」「速い車」といった様々な回答が出ました。「『すごい』はいろいろな意味を持っている」「すごいは形容詞だね」という気づきから、抽象的な言葉よりも具体的な表現の方が相手に正確に伝わることを、児童たちは自ら学んでいきました。
小川先生は、児童たちに「チャレンジしてくれる人」と声をかけ、自ら挙手することを促しています。この「チャレンジ」という言葉には、正解を求めるのではなく、間違ってもよいから自分の考えを発言できる雰囲気を作りたいという思いが込められています。
「自分という枠の中でなく、相手や、他のひとのことを、少し考えてみませんか。」これは私がよく使う言葉です。先日、私の授業では、自分の意見を述べた後、友達の異なる視点に驚いていた児童がいました。「そうか、同じ文章でも人によって見方(解釈)が違うんだね」と気づいた瞬間、その児童は他の意見にも耳を傾け始めました。多様な考えを知ることで、自分の視野が広がっていく様子がはっきりと見て取れました。
このニュース教室の真の目的は、講師が答えを与えるのではなく、児童同士が意見を交わし、自らの気づきを得られるようにすることです。言葉の持つ力を理解し、適切に使いこなせる力は、これからの時代を生きる子どもたちにとって何よりも大切な能力の一つです。
日々の小さな「チャレンジ」の積み重ねが、浜松の子どもたちの未来を切り拓く力になると信じています。
2025/04/02 Category | blog
« 極上の文章に触れる体験 〜春の読書講座「ゴッホの手紙」から〜 中学生の心に寄り添う – 思春期の親子関係を考える »