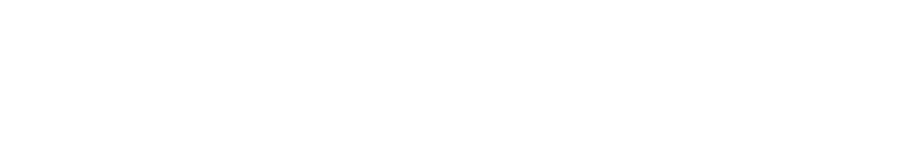【前編】経済的不安の時代だからこそ、子どもの「視野と変化対応力」を育てる子育て
世界情勢が揺れる今、トランプ関税による経済の混乱が続いています。株価の急落、報復関税の応酬、石破首相が「国難」と表現するほどの状況。子育て世帯にとって、将来の不透明さは決して小さな不安ではありません。
しかし、このような時代だからこそ、子どもたちに「視野の広さ」と「変化への柔軟な対応力」を育むチャンスがあると捉えることもできます。
点数のための勉強から、意味を見出す学びへ
学校のテストは確かに大切ですが、それ自体が目的になってしまうと、子どもの学びは表面的なものになりがちです。本当に大切なのは、「なぜ学ぶのか」「この知識が社会の中でどんな意味を持つのか」を考える視点です。
たとえば、ある生徒が定期テストの勉強中に「なぜこれを覚える必要があるのか」と疑問を持ちました。そこで、その知識がどのように現実の課題と関わるかを一緒に考えてみると、「自分は環境問題に関心がある。この化学の知識は、それに役立つかもしれない」と気づいたのです。この気づきが、彼の勉強への姿勢を根本から変えました。
このように、「学んだ先にある世界」に目を向けることで、学びは自分の人生と深く結びつくものになります。
親ができる具体的な問いかけ
では、親としてどんな声かけができるのでしょうか。
一つの方法は、週末の食卓など、穏やかな時間を使って、次のような問いを投げかけることです。
- 「あなたは将来、どんな仕事や生き方をしたいと思っている?」
- 「その夢に、今の勉強がどうつながっていると思う?」
このような問いは、子ども自身が「社会の中で自分はどうありたいか」という軸を持つきっかけになります。勉強は単なる知識の詰め込みではなく、未来を築くための手段だと実感するのです。
不安の時代だからこそ、問いを明確に持つ
今のように社会が不安定なときこそ、私たち大人が「何を子どもに伝えたいか」「どんな力を育てたいか」を明確にしておくことが重要です。そして、そのために必要な問いは、「何を学ぶか」ではなく、「なぜ学ぶか」「学びをどう使うか」という視点にあります。
この問いは、すぐに答えが出るものではありません。けれど、子どもがその問いに向き合い続けることで、時代の変化に左右されない「自分軸」が育っていきます。
次回は、「不確かな時代を生きる力を育む—親として何ができるか」と題して、子どもが変化の激しい社会を生き抜くために必要な力と、その育て方について考えていきます。
未来を見据えた子育てを、私たち大人が一歩ずつ模索していきましょう。
2025/04/08 Category | blog
« 中学生の心に寄り添う – 思春期の親子関係を考える 【4/8付】意見を育てるニュース教室 – 自分事として考える力 »