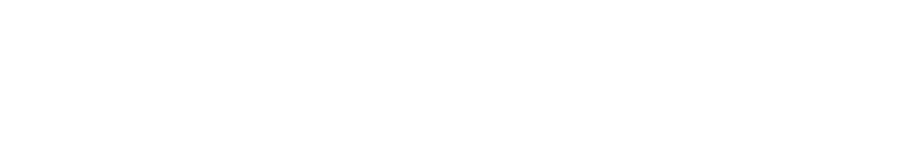親の願いか、子どもの意思か—中学受験の主体性を考える
浜松西高中等部や静大附属浜松中など、地域の難関校を目指す際に最も大切なことは、「誰のための受験なのか」という問いではないでしょうか。
以前、まなび研究所に通ったAさんは当初、「親が勧めるから」「周りの友達が受験するから」という他者主導の理由で中学受験を考えていました。そこで私たちは、Aさん自身が学校選びの主体となるよう、各学校の特色や学びの環境について自分で調査するよう促しました。
すると彼は、インターネットや学校説明会で得た情報を整理し、「浜松西高中等部の探究学習で自分の好きな理科の研究が深められる」という自分なりの理由を見つけたのです。その瞬間から、彼の学習への姿勢は劇的に変わりました。親に言われるのではなく、自分で選んだ目標に向かって自ら学ぶ喜びを発見したのです。
中学受験は「親の願望実現」ではなく、子ども自身が「自分の選択」として取り組むことで、生涯の学びの姿勢の基礎となります。まずは子どもに「なぜその学校に行きたいのか」を自分の言葉で語らせてみましょう。その答えが見つからないなら、まだ受験の準備は始まっていないのかもしれません。
「子どもの才能の種を見つけて『原石』を磨く」ことが健全な親子関係の基本です。けれども、その先には何があるのでしょうか。私はいつも子どもたちに問いかけます。「あなたが学んでいることは、将来誰かの役に立つことにつながりますか?」と。
学びの本質は、ただ知識を身につけることではなく、その先にある社会への貢献にあります。浜松西高中等部や静大附属浜松中で学ぶことが、将来、社会が抱える課題を解決する奉仕の精神を宿す人間へと成長する一歩となることを、子どもたち自身が意識できたとき、受験勉強は単なる試験対策ではなく、人生の土台づくりとなるのです。
私は、これからも子どもたちの視座を高める指導をし続けたいです。ここにブレはありません。小さな目標から始めて、いつか大きな社会貢献につながる学びの種を蒔くこと—それこそが本当の意味での受験指導だと信じています。
2025/04/11 Category | blog
« 【後編】経済的不安の時代だからこそ、子どもの「視野と変化対応力」を育てる子育て 「目標という灯台」が中学生の学びを変える時 »