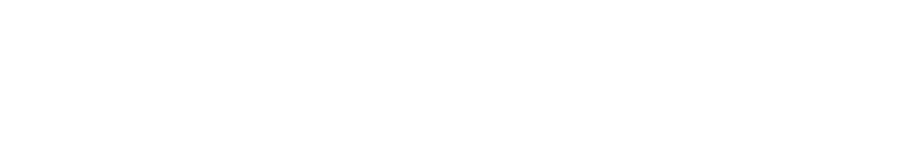「目標という灯台」が中学生の学びを変える時
コンサルティング中に、中学生と話し合いながら目標設定をしていると、ある瞬間が必ず訪れます。「次の数学のテストで45点以上(50点満点)取って、学年で10位以内に入る」というような具体的な数字が決まった瞬間、それまでなんとなく漠然としていた表情が、キリッと引き締まるのです。
目の前で起こるこの変化は、いつ見ても心を打たれます。具体的な目標が決まった瞬間、それまでぼんやりとしていた「勉強」という行為に、明確な意味が生まれるからでしょう。
大切なことは解像度を上げること。同じ数学の問題集でも、ただ「やっておきなさい」と言われた時と、「この問題集をマスターすれば次のテストで45点が狙える」と伝えた時では、中学生の取り組み方が全く異なります。
目標がない勉強は、ただ漠然と時間を消費するだけ。しかし具体的な目標を持った勉強は、一問一問に意味が宿ります。「この問題が解けるようになれば、テストで2点上がる」という実感が、集中力を高め、学習効率を飛躍的に向上させるのです。
私たち大人も振り返ってみれば分かることですが、「なんとなく頑張る」と「具体的な目標に向かって頑張る」では、使うエネルギーの質が全く違います。中学生も同じで、目標があるかないかで、同じ3時間の勉強でも得られる成果が大きく変わってくるのです。
ある中学1年生の男子は、具体的な目標設定をした後、こう言いました。「先生、目標が決まると、なんか勉強のやり方が変わる感じがします。何をやるべきか、自分で考えるようになるんです」
これこそが、まさに自立した学習者への第一歩。目標を自分で意識することで、「どうすれば効率よく点数を上げられるか」という思考が始まり、受け身だった勉強が能動的なものへと変わっていくのです。
親御さんの中には「うちの子はまだ自分で目標を持てない」と心配される方もいらっしゃるでしょう。でも、それは当然のこと。最初から自分で目標を設定できる中学生は稀です。大切なのは、まずは親や教師が一緒に具体的な目標を考え、その達成に向けてサポートすること。そして少しずつ、目標設定そのものを子ども自身ができるように導いていくことなのです。
「はっきりとしたゴールがないと、『やるべきこと』と『やらなくてよいこと』というタスクの選択ができなくなる」というのは、大人も子どもも同じです。中学生にとって、具体的な目標は学びの道しるべとなり、無駄な遠回りを避ける助けになります。
目標設定において大切なのは、「達成可能なチャレンジ」であること。今の実力より少し高い壁に挑むことで、子どもは成長します。逆に、あまりにも高すぎる目標は挫折感を生み、低すぎる目標は成長の機会を奪ってしまいます。
お子さんと一緒に、「次のテストではどんな点数を目指す?」「そのためには、どんな準備が必要かな?」と話し合ってみてください。その会話の中で、お子さんの表情が変わる瞬間を、きっと見ることができるでしょう。その変化こそが、自立した学習者への第一歩なのです。
どんな壁も、少し離れて見れば登れる道が見えてくる——この言葉を胸に、お子さんの成長を長い目で見守っていきましょう。具体的な目標という灯台があれば、どんな嵐の夜でも、きっと港にたどり着けるのですから。
2025/04/12 Category | blog